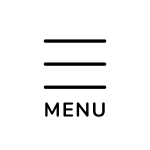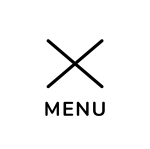アフリカ文化財返還の動き、過去の略奪から未来へ?アフリカ文化財返還の現状
19世紀の略奪から現代まで、アフリカ文化財返還の動きが加速! 欧米の博物館に眠る文化財の多くは不法に持ち去られたもの。人権意識の高まりを背景に、フランス、ドイツ、イギリスなどが返還を進める。しかし、所有権、返還方法、ビザの問題など、課題も山積。歴史の記憶を正し、公正な社会を築くための、文化財返還の行方を追う。

💡 植民地時代に略奪されたアフリカ文化財の返還を求める動きが活発化していることを知ることができます。
💡 フランス、ドイツ、イギリスなど、欧州各国の返還事例を通して、具体的な動きを把握できます。
💡 歴史的な課題や今後の展望について理解を深め、未来へと繋がる議論に参加できます。
本日はアフリカの文化財返還に関する記事をお届けします。
まずはこの記事で、どのようなことが分かるのか、3つのポイントを簡潔にご紹介します。
歴史の闇と文化財
アフリカの文化財、どこに?返還が進まない理由は?
欧州に多く、不法入手と国際法が壁。
19世紀後半の植民地化時代に、アフリカ大陸から大量の文化財が持ち去られました。
これらの文化財の返還を求める声が長年上がり、現在、大きな動きとなっています。
公開日:2021/05/14

✅ 欧州では、植民地時代に略奪したアフリカ文化財の返還を求める動きが活発化しており、ドイツはベニン・ブロンズのナイジェリアへの返還を決定。
✅ ドイツは、まずは所蔵するベニン・ブロンズのリストを公開し、デジタルライブラリーを構築する一方、返還する作品を選別し、一部は自国での展示も検討。
✅ ナイジェリアでは新たな美術館EMOWAAの建設が進められており、ドイツは2022年に最初の返還を実施することを目指している。
さらに読む ⇒NewSphere - 世界と繋がるミレニアル世代に向けて、国際的な視点・価値観・知性を届けるメディアです。出典/画像元: https://newsphere.jp/world-report/20210515-1/ドイツのベニン・ブロンズ返還決定は、画期的な出来事ですね。
デジタルライブラリーの構築や返還作品の選別といった、具体的な取り組みも興味深いです。
19世紀後半の植民地化時代、アフリカ大陸から大量の文化財が持ち去られ、その多くはヨーロッパに渡りました。
現在、サブサハラ・アフリカ由来の文化財の90%以上がアフリカ大陸外に存在し、その多くがヨーロッパの博物館に所蔵されています。
しかし、これらの文化財の多くは不法に持ち去られたものであり、返還を求める声が長年上がっていました。
第二次世界大戦中のナチスによる略奪文化財の問題も、文化財保護の国際条約が過去の案件には適用されず、返還が停滞していました。
しかし、1998年のワシントン原則によってナチス略奪文化財の返還が促進され、NPO法人CLAEなどが中心となって活動を進めました。
すごい!歴史的背景とか、具体的な動きがすごく分かりやすかったです!返還への流れが加速しているんですね!
転換点:アフリカ文化財返還の動き
アフリカ文化財返還、欧米を動かしたものは?
過去の植民地支配への反省と外交重視。
2017年のフランス・マクロン大統領の演説を契機に、アフリカ文化財返還の動きが加速しました。
人権意識の高まりも、大きな後押しとなっています。
公開日:2021/10/29

✅ フランスは129年前に略奪したベナン(旧ダホメ王国)の美術品26点を来月返還する。
✅ 返還対象は王を象徴する像や王宮の扉、玉座などで、現在はパリのケ・ブランリ美術館に所蔵されている。
✅ マクロン大統領は、アフリカとの関係改善のため、今後も一部の美術品を返還していく考えを示している。
さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASPBX6K5FPBXUHBI00K.htmlフランスによる返還は、まさに転換点と言えるでしょう。
過去の過ちを認め、アフリカとの関係改善を目指す姿勢は素晴らしいと思います。
長らく消極的だった欧米諸国でしたが、2017年のフランス・マクロン大統領による演説が転換点となりました。
アフリカ文化財の返還に向けて動き出し、専門家による調査報告書に基づき法整備を急ぎ、返還を進めました。
この動きは、人権差別撤廃の世論の高まりやBLM運動、対アフリカ外交の活発化を背景に欧米を中心に加速しています。
特に、過去の植民地支配への反省と対アフリカ外交の重視が背景にあります。
おお、フランスも動いてるんですね!過去の反省から、関係改善しようとする姿勢は、良いと思います!
次のページを読む ⇒
欧米の美術館で進む文化財返還。過去の略奪への反省から、アフリカを中心に返還が加速。所有権、返還方法など課題も。歴史的正義と未来への希望を描く。